■怪我には2種類ある
ダンスにしてもスポーツにしても、怪我は大きく2種類に分類できます。
それが「外傷」と「障害」です。
外傷とは、ジャンプの着地時に足を捻ったり、他人とぶつかったりして発生する捻挫・打撲・骨折などの一時的な怪我を指します。
一方、障害とは、繰り返しの練習や長時間のレッスンによる疲労の蓄積によって引き起こされる、慢性的な痛みや骨・関節の異常を含みます。
特に注意すべきは障害です。
これを放置すると、ダンスを長期間休まなければならなかったり、最悪の場合はダンスをやめなければならなくなってしまうこともあるのです。
■ダンス練習による「破壊と修復」
「練習とは、体を一時的に“破壊”する行為」だと言われています。
ステップ練習やジャンプ、ターンといった反復動作によって筋肉や関節には大きな負担がかかります。
この“破壊”された体を修復するために欠かせないのが、栄養ある食事と質の高い休養です。
この「破壊→修復→成長」というサイクルがうまく回っていると、身体は確実に成長します。
でも、練習量が多すぎて食事や睡眠が追いつかない状態が続くと、回復が追いつかず、成長が止まるどころかパフォーマンスの低下や怪我のリスクを高めてしまうのです。
■現代の子供はオーバーワーク気味?
近年、子どもたちは沢山の習い事を掛け持ちするケースが増えています。
色々な事に興味をもち、挑戦することは素晴らしいですが、その一方で、休養や食事が不足しがちになり、身体への負担が増しています。
子どもの体は大人とは違い、発育途中であるため、適切なケアを行わなければすぐに不調が表れます。
「もっと上手くなりたい!」「いろいろな事に挑戦したい」という気持ちは大切ですが、それと同じくらい「自分の体の状態を知ること」も重要なのです。
■「負荷耐性」を理解しよう
スポーツ医学の分野で注目されている概念に「負荷耐性」というものがあります。
これは、どれだけの練習量や負荷に対して、体が問題なく適応できるかという能力を指します。
この負荷耐性は、トレーニングの質、栄養、休養のバランスによって高めることができます。
逆に、ハードな練習ばかりを続けていて、食事や休養が追いついていないと、負荷耐性は低下し、体のどこかに不調が現れやすくなります。
特に成長期の子どもたちは、体の中で最も負荷に弱い「骨格系」に問題が出やすいとされています。
骨がまだ柔らかく、関節も未発達な段階で強い負荷をかけると、疲労骨折や関節の炎症を引き起こす危険性が高まります。
■身長の伸び=大人の体ではない
一見、身長が伸びてきて体が大きく見えると「もう大人と同じ練習ができる」と思いがちです。
しかし、実際には筋肉や関節、骨の密度などはまだ発展途上。大人のような練習メニューを無理にこなすのは、非常に危険です。
特にダンスは、体のあらゆる部位を使う全身運動。
ジャンプの着地やフロアワークなどで強い衝撃がかかることもあり、負荷の分散がうまくできないと、一部の関節や骨に過剰なストレスがかかってしまいます。
■特に注意したい体の部位
ダンスにおいてよく問題が生じやすい部位は以下の通りです。
-
足首・膝:ターンやジャンプの着地で捻りやすく、痛みが出やすい
-
腰:長時間の姿勢維持や反復動作で疲労が蓄積されやすい
-
肩・手首:フロアムーブや転倒時の衝撃で脱臼・骨折リスクがある
■焦らず、段階的に成長を
ダンスの上達には時間がかかります。
そして、そのプロセスの中で身体的な成長と技術的な成長を「バランスよく」進めていくことが重要です。
成長期の体はとてもデリケート。無理な練習を重ねてしまうと、将来的な可能性を閉ざしてしまうことにもなりかねません。
指導者や保護者は、子どもの「今の状態」に目を向け、適切な休養と栄養、そして段階的な負荷調整を意識していくことが求められると考えています。
アートグルーヴの講師たちは、そういった身体や成長のサインも丁寧に見極めながら、生徒一人ひとりに合わせた指導を心がけています。
安心して踊り続けるためにも、心と体、両方の成長を大切にしていきたいですよね。

5月16日(金)のレッスンは
| 時間 | クラス | 担当インストラクター |
|---|---|---|
| 18:00~19:00 | ジュニアブレイキン | ISAMU |
| 19:00~20:30 | ヒップホップ | SARA |
| 20:30~22:00 | ロックダンス | GO |





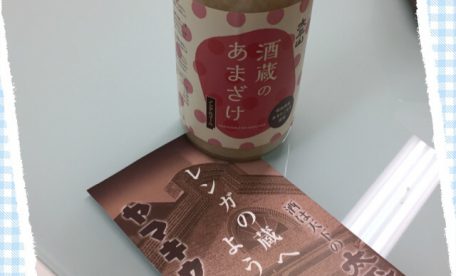



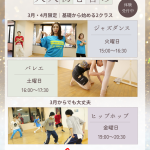
























この記事へのコメントはありません。