「地頭がいい」とはどういうこと?
最近よく耳にする「地頭がいい子」。
これは単に「頭の回転が速い」とか「勉強ができる」ということではなく、
物事の本質を理解し、応用しながら問題を解決していける“思考力”や“柔軟性”を指します。
特に私が日米で教育に関わる中で実感しているのは、地頭の良さには言語力の高さが深く関係しているということです。
地頭の良さは、才能ではなく「後天的に育てられる」
「うちの子、地頭が良くないのでは…」と不安に思う必要はありません。
地頭は、生まれつきの才能ではなく、日々の環境や経験で育てていける力です。
そのカギを握るのが、「言葉を理解し、活かせる力」=言語力なのです。
言語力とは、
-
話を正しく理解し、
-
自分の中に落とし込み、
-
再現したり応用したりできる力。
つまり、コミュニケーションの中で学び、考え、発信するサイクルを回していける力です。
言語力を伸ばすには「イメージする力」が必要
言葉だけでは、なかなか人の心や行動は動きません。
必要なのが「イメージする力」です。
たとえば、「楽しい」と言われたとき、ある子は「笑顔の自分と友だちが遊ぶ様子」を思い浮かべたり、
別の子は「お気に入りの音楽に乗って踊る姿」を想像するかもしれません。
この言葉をイメージ化する訓練は、読書や対話だけでなく、実はダンスやバレエのレッスンでも磨かれていくのです。
バレエやダンスが「言語力・想像力」を育てる理由
ダンスやバレエのレッスンでは、先生がよくこのような言葉を使います。
-
「ふんわり跳んでみよう」
-
「パキパキ動いてみて」
-
「頭のてっぺんから糸で引っ張られているように」
-
「まあるく回ってごらん」
これらは、言葉を通して“動きのイメージ”を引き出す表現です。
「ふんわり」と言われて、それがどういう状態かをイメージできる子は、それを体で表現しようとします。
言葉を“体で理解する”練習にもなっているのです。
また、音楽を聞いたときに「優しい感じ」「元気な感じ」などを感じ取る感性も、想像力の一部。
ダンスは、言葉・感覚・身体表現を総動員する活動であり、自然と言語力・想像力が育つ環境なのです。
問題解決力もダンスで伸びる?
地頭の良さとよく結びつけられるのが「問題解決力」。
この力は、
-
言葉(情報)を正しく理解し、
-
分析し、
-
本質を見極めて、
-
判断・行動する
というプロセスで培われます。
ダンスのレッスンでは、
-
振付を覚える
-
ミスを修正する
-
自分で動きを考える
-
チームでそろえる
など、常に小さな「課題解決」を繰り返しています。
楽しみながら自然と“考える力”が養われているのです。
共感力の高い子は「国語力」との相性が良い
「人の気持ちに敏感」「空気を読むのが得意」な共感力の高い子どもは、言語の微妙なニュアンスを感じ取る力があります。
このような子には、「国語」にフォーカスした学びが非常に効果的。
国語力は、他の教科を学ぶ上での“土台”です。
言葉の意味や背景を読み取る力がつくと、算数の文章題も読み違えなくなります。
そしてその「言語力・国語力」の感覚を、ダンスやバレエのレッスンの中でも培えるのです。
言葉とカラダで育つ「本当の地頭」
地頭を育てるには、
-
日常の中で言葉に触れ、
-
想像力を働かせながら、
-
自分の中に落とし込む体験の積み重ねが大切です。
それを楽しく実践できる場が、ダンスやバレエのレッスン。
「ふんわりってどういうこと?」「この音楽ってどんな感じ?」と考えながら動く経験こそが、
地頭=思考力・言語力・想像力を育てる近道なのです。
\体験レッスン受付中!/
当スタジオでは、想像力や言語力を育てる視点からもバレエ・ダンスレッスンを行っています。
共感力の高いお子さんにもぴったりのレッスンです。まずはお気軽に体験からどうぞ!


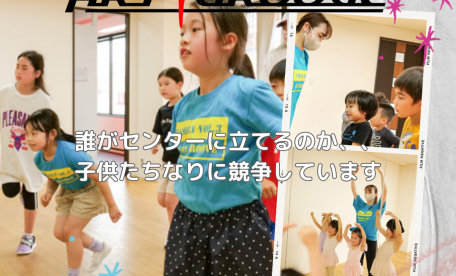
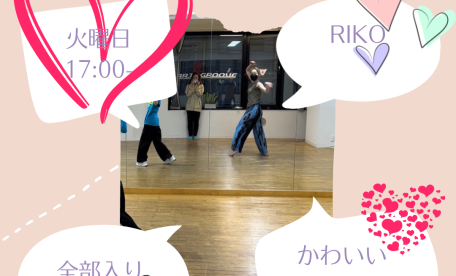
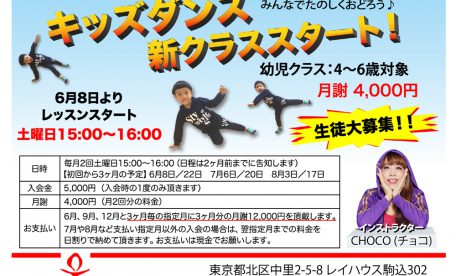

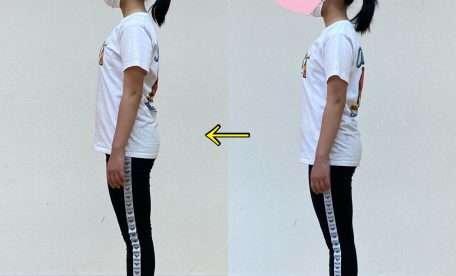

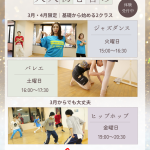
























この記事へのコメントはありません。